ブログ
BLOG
2025/10/31
ブログ
鉄の音の向こうで感じた、まちの空気の変化。
朝の空気がすこし冷たくなってきた。
工場のシャッターを開けると、秋の光が鉄の表面に反射する。
その光を見ながら、今日も一日が始まる。
機械の音、溶接の光、鉄の焼ける匂い。
いつもの風景だが、ふとした瞬間に「まちの空気」が変わったように感じる日がある。
数日前のニュースでは「上越市長選が終わった」と報じていた。
特別に政治を語るつもりはないけれど、こうした出来事を通して、
「上越というまちがどこへ向かおうとしているのか」を考えるきっかけにはなる。


日常の中にある“地域の今”
現場では、社員がそれぞれの持ち場で黙々と作業を続けている。
火花が散る音の合間に、「最近、駅前に新しい店できたね」とか、
「このあたりも空き地が増えてきたな」なんて言葉が飛び交う。
そんな何気ない会話のひとつひとつに、
この地域が抱える“今”が映っている気がする。
まちの話題を口にすることは、仕事とは関係ないようでいて、
実はとても近い。
人の流れが変われば、仕事の流れも変わる。
道路が整えば、現場へのアクセスが良くなり、
イベントが増えれば、看板や設備の仕事が増える。
私たちの仕事は、まちの変化とともに動いている。
鉄工所から見えるまちの姿
福田鉄工は、上越で長くものづくりを続けてきた。
プラント設備、建築鉄骨、溶接、製缶。
仕事の種類は多いが、どれも「人の暮らしの土台」を支える仕事だ。
新しい建物、企業の工場、地域の施設。
完成したあとには人が集まり、使い、そこに生活が生まれる。
自分たちのつくったものが、そうした日常の中に静かに残っていく。
それがこの仕事の醍醐味でもある。
大きな出来事よりも、
日々の現場で感じる小さな変化こそが、地域の姿を映している。
たとえば、近所で新しい工事が始まったり、
地元の企業が新しい取り組みを始めたり。
そんな動きが見えると、「上越もまだまだ変わっていける」と思う。
“まちの元気”は、現場に伝わる
まちの雰囲気が明るいと、仕事にも勢いが出る。
反対に、停滞した空気のときは、依頼のトーンもどこか落ち着いてしまう。
鉄工所の仕事は、地域の経済や人の動きに敏感だ。
たとえば、新しい商業施設ができると、
それに関連して鉄骨・看板・配管など、さまざまな仕事が生まれる。
逆に、建設が止まると、そこに関わる多くの職人の仕事も止まる。
だからこそ、まちの「元気」はただの雰囲気ではない。
現場の一人ひとりの暮らしに、確実に届いてくるものだ。
鉄のように見えて、実はとても“人間的”な仕事だと思う。
若い世代と未来へのまなざし
最近は、地元でも「ものづくりの仕事に興味がある」と話す若い人が少しずつ増えてきた。
直接見学に来るわけではなくても、SNSやイベントを通じて、
「鉄工所ってこういう仕事をしてるんだ」と知ってもらえる機会が増えている。
“見せる”ものづくりは、これからの地域には大切だと思う。
技術だけでなく、そこにある人の思いや手の温もりを感じてもらうこと。
それが、次の世代へのバトンになる。
福田鉄工としても、いつかそうした若い人たちが気軽に
「ちょっと見に行ってみよう」と思えるような場をつくっていきたい。
ものづくりの現場が閉じた世界ではなく、
地域とつながる“ひらかれた場所”になるように。
「変わる」ことと「続ける」こと
工場の中では、毎日少しずつ違う音がする。
天気や湿度、使う材料によって、同じ作業でも微妙に感触が変わる。
それでも積み重ねていくうちに、ひとつの形になる。
まちも同じだと思う。
急に変わることはないけれど、
人が動き、声が交わり、小さな工夫が重なっていくうちに、
気がつけば少しずつ良い方向へ進んでいる。
鉄の仕事は、そうした「ゆっくり変わるもの」を信じる仕事だ。
焦らず、手を抜かず、確実に積み上げる。
その姿勢を、これからも大切にしたい。

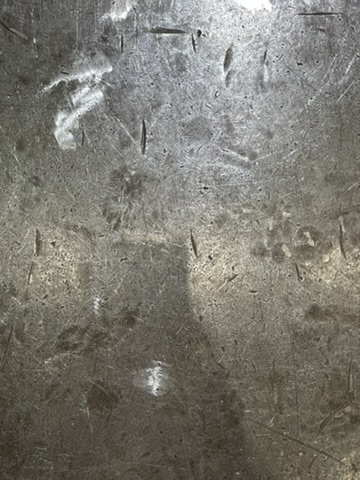
鉄の光と、まちの光
夕方、作業を終えて外に出ると、空が少し赤く染まっていた。
工場の中ではまだ、誰かが最後の仕上げをしている。
その光が外まで漏れて、まるで灯りのように見える。
あの光は、単なる溶接の火花ではない。
上越というまちのどこかで、
誰かの暮らしを支える“光”でもある。
政治のことは詳しくなくても、
こうして日々の仕事を通じて、
自分たちなりにまちと関わり続けることができる。
光と鉄で、今日もかたちをつくる。
それが、福田鉄工の変わらない日常であり、
このまちへの小さなエールでもある。



